|
「悲観主義者が、星々の神秘を探求したり未知の土地に航海したり、人の魂にふれる新しい扉を開いたことはこれまで一度もない」(2007年12月28日付け毎日新聞コラム"発信箱")
|
|
これは、そのヘレン・ケラーの残した言葉だそうで、今年は彼女が没して40年目になるということです。
見えない・聞けない・話せないの三重苦(この言葉はあまり好きではないのですが・・)を背負った彼女のことは、いまさらお話しすることも無いでしょう。彼女の生涯は、彼女とともに苦難と喜びの道を歩いてきた生涯の教師であるアン・サリバン女史の人生をささげた日々時々とともに、多くの本、映画や演劇などにもなっています。"知ることの喜びを追い求め、扉を開き続けた人"ともいえますね。
|
さて、この悲観主義者にたいして それでは楽観主義者であれば"人の魂に触れる新しい扉"を開けられるかといえば、どうも そうとも言い切れないように思えます。
悲観主義者というよりは、悲観的に物事を捉えやすく何かにつけて否定的な考え方に陥りやすいタイプの人、また、楽観主義者というよりは、何が起こったところでまずは率直にその事実を受け入れ、できるだけのなるべくより良い対処を考えようとし実行する人、と私は考えます。
あなたは 悲観的な傾向のある人ですか?それとも楽観的に物事を捉えるほうですか?
実は、私はあるときまで少々偏った悲観的感覚の持ち主でした。
どうしてそうなったのかは分かりませんが、子供であっても日々自分に起こる出来事のいちいちに、いつもどこかでおどおどしていて、家庭と学校においては何かにつけて起こることの一つ一つに、いつも一番そうなってほしくないことをまず考え、それにどんどん勝手な思い込みが絡み付いて膨らみ、終には何をしても何の意味もないと思えると、ソレについてはなんの期待せずに忘れようとしたり、こまごましたことに及ぶまでも、これっぽっちの希望も喜びもないような結果を半ば信じて疑わないようなときが長い間、大人になってもありました。 |
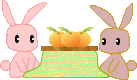
コタツにみかんは
冬のお約束だね!
|
何かを期待して期待したとおりになどなることは殆どないのだ、ということに早くも気付いていた当時の自分は、その期待がどれほど淡いものであれ、結果「打ち砕かれる」という状態を味わいたくない、耐えたくない、極力避けて通りたいと思っていたようです。
ですが、そのどれもが、大人になった今思うと それほどたいしたことではないことのほうが多かったように思います。
それがどうして 今のように何があったところで"えっ?"と思いはしてもそれほどの動転もせず、とんでもないことが起こったところで自分でも不思議なくらい淡々とそれを見つめていられるようになったのかといえば、まずは年を取った(なんども似たような経験をしてある程度の現実的な予想を立てられるようになった。)からでしょうし、ここまで生きて来てしまったことで、何があろうと死ぬその時までは日々は当たり前に過ぎていくのだということを知ったからであり、様々な形でこの世界に生きるものには、どうやら目に見えない手の介在があるらしいと思えるような経験が幾度かあったりして、「生きる」ことそのものに必要以上の恐れや不安を抱かずにいられるようになったからではないかと思うのですね。
自分と人が同じとは思いませんが、経験を積むことで安心や予想するための基準を得、それによってできる心の準備が余裕を生み、それをもって物事に当たることができるようになるように思います。そういう今の自分を子供のころの自分が見たら、ずいぶんとお気楽な人間に見えるでしょうね。
|
|
生きるということ、時を重ねるということは、そんな風に自分や周りに起こる喜怒哀楽を、痛みのあることでさえも抱き留めて目をそらさずに見つめ続けられるようになっていくように思えています。
そして、そういうことが積み重なり、あることへの理想や期待が生まれて何かを形にしていくための原動力になっていくのでは・・とも。それがきっと『人の魂にふれる新しい扉を開く』ことにつながっていくのではないかと思えてなりません。 |
「秘密の花園」は、長いことその存在を不明にしていましたが、好奇心の強い冒険心のある少女が扉を発見して開いたことから、終には人の心の喜びと慰めの花園へと生まれ変わります。
2008年にはそんな風に皆のための花園の扉が開かれるようにと祈ります。
|